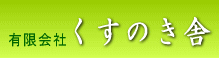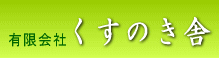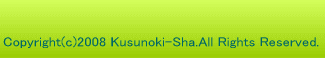|
|
|
 |
|
|
|
校正でもっとも基本的なことは、校正刷りが原稿どおりに正確に組版されて
いるかどうかを確かめることです。
正しく組版されていなかったら、赤字で訂正します。
これを「原稿引き合わせ」といいます。
また、再校以降で、赤字が正しく差し替えられていることを確認する作業を
「赤字引き合わせ」といいます。
くすのき舎の校正者は、原稿引き合わせを中心にした校正技能検定(4級・3級)
に合格した者がほとんどです。
正確な原稿引き合わせが校正ではもっともたいせつであると心得て、拙速を
排した丁寧な仕事を心がけています。
|
|
|
|
|
|
|
|
引き続きこちらもご覧ください
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
著者が書き誤った誤字や脱字、語句の使い方・使い分けの誤りや疑問
を指摘することもたいせつです。
校正刷りの文章を、一字もゆるがせにせずに読んでいきます。
この作業のことを「素読み」といいます。
*文字の誤り
「漢字の字形の誤り」「ひらがなの脱字や、誤った文字の挿入(衍字)を
指摘します。
*ことばの誤り
「てにをは(助詞)の誤り」「動詞や助動詞の活用や使い方の誤り」「慣用
表現の誤り」を指摘します。
たとえば、ら抜きことばを助動詞の使い方の誤りとみれば、指摘して著者
と編集者の判断にゆだねます。
*外国語の誤り
「外来語の表記の誤り」「外国語のつづりや文法上の誤り」を指摘します。
*表記の取り決めに沿った整理
原稿整理で整理がもれていたことがらを指摘します。
「数字の表記のしかたの整理」「記号や約物の使い方の整理」をします。
17か、一七か、十七か。1ヵ月、1ヶ月、1箇月、1か月、1カ月、1ケ月の
どの表記を採用するか、といったことを、原稿整理方針の取り決めに沿って
ただします。
*矛盾したことが書かれていたら指摘する
「数字の矛盾」「時系列の矛盾」「その他の内容の矛盾」があれば、それを
指摘します。
フィクションの作品では、舞台設定上の内容矛盾の指摘が重要になります。
これらを編集者に疑問として提出します。
編集者は、必要なことは著者に問い合わせて疑問を解決し、赤字にします。
また、素読みでは、「校閲」の項で述べる内容的な誤りの指摘や、確認作業を
行なうこともあります。
|
|
|
|
|
|
|
|
引き続きこちらもご覧ください
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
原稿引き合わせは、原稿を忠実に再現することをめざします。
一字の誤りのない再現をめざしておこなうことです。
1冊10万字の一字もゆるがせにしない正確さは、99.999%以上の確かさ
ということです。
目標を胸に、校正という仕事のむずかしさを実感しながら、わたしたちは
日々仕事をしています。
人間のすることに誤りはつきものです。人間は機械のように正確にはなり
えないと思います。
しかし一方で、著者の意図を汲んでこそ、校正は作品を正確に再現できる
のだと思います。
校正は、このように機械ではできないことでもあるのです。
|
|
|
|
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
素読みをするときにも、綿密に校正刷りを読まなければなりません。
拙速を排して着実に読み進めてこそ、文字やことばの誤り、内容の矛盾が
指摘できるのです。
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
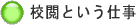 |
|
|
|
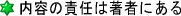 |
|
|
|
作品(著作)の内容の責任は著者が負います。
責任を負うからこそ「著作権」があるのです。
しかし、一方で出版社(発行元)の側が、作品の内容の正しさをみずから
確認することがあります。
内容の信頼性を確認するこの作業を「校閲」といいます。
校正者がこの作業を校正と同時に請け負うこともあります。
|
|
|
|
 |
|
|
|
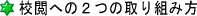 |
|
|
|
校正者の校閲への取り組み方には、大きく分けて2通りあります。
1.内容や表記について疑問を抱いた点についてのみ、参考資料にてらして
検証する
2.ある範囲のことがらについて、参考資料にてらして検証する
この2つです。
|
|
|
|
 |
|
|
|
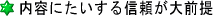 |
|
|
|
1.は、内容を検証するときに、つねに必要なことです。
合理的で具体的な疑問があるときに、その裏づけをとることは、「校閲」には
欠かせないことです。
専門家が執筆しているのですから、内容についてほぼ信頼できるというのが、
大前提となります。
大前提をもとにしつつ、疑問のある箇所や要所につき資料に拠り裏づけをとる
のが、校閲の基本的な職分です。
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|
 |
|
|
|
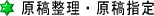 |
|
|
|
小社では原稿整理・原稿指定の仕事も、一部、請け負っております。
これは、つぎの2つに分かれます。
1.原稿整理・原稿指定だけを請け負う
2.原稿整理・原稿指定から校正までを一貫して請け負う
小社では後者のほうが多いケースです。
時間との兼ね合いもありますが、この作業は、素読みや校閲にかかわる
整理は校正段階でもできることを前提にして、形式的な整理に重点をおく
ことがあります。
形式的な整理には、数字・記号・約物の表記法を整理したり、引用文献の
本文中の体裁や注での表示のしかた、図表の番号の整理、図表の大きさ
や組み方の指示、などがあります。
表記の統一が必要ならば、これも原稿整理・原稿指定の仕事の1つとして
行ないます。
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
著者に原稿を書いてもらい、本として仕上げるまでの工程の全般にわたる実務
のことを、編集制作といいます。
場合によっては、原稿の制作から、編集制作者が何らかのかかわりをもつことも
あります。
校正は、編集制作の一部という位置づけができます。
わたしたちが、編集制作の全般にわたってかかわることは、あまりありません。
校正を中心にすえた、校正プロダクションであるからです。
しかし、校正専門だからこそ、内容についての吟味には、その職能を活かした
方法と実践の蓄積があります。
別記のように、原稿整理・原稿指定から担当することもあります。
編集担当の方と連携し、著者に問い合わせをして、内容面での問題解決までを
担当したこともあります。
また、フリーランスの編集者や、編集プロダクションとの交流もあります。
必要な体制をつくるための、ご協力もできるかと思います。
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
たとえば、つぎのような仕事が、校正や編集制作の周辺で発生します。
1.リライト
校正での原稿の吟味作業を発展させて、リライトを担当することもできる場合
があります。
より自然で読みやすい、親しみやすい文章づくりに協力できるかと思います。
2.テープ起こし
これは、専門会社もあります。
|
|
|
|
戻る
|
|
|
|
 |
|
|
|
  |
|
|
|
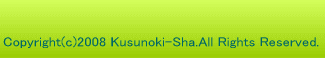 |
|